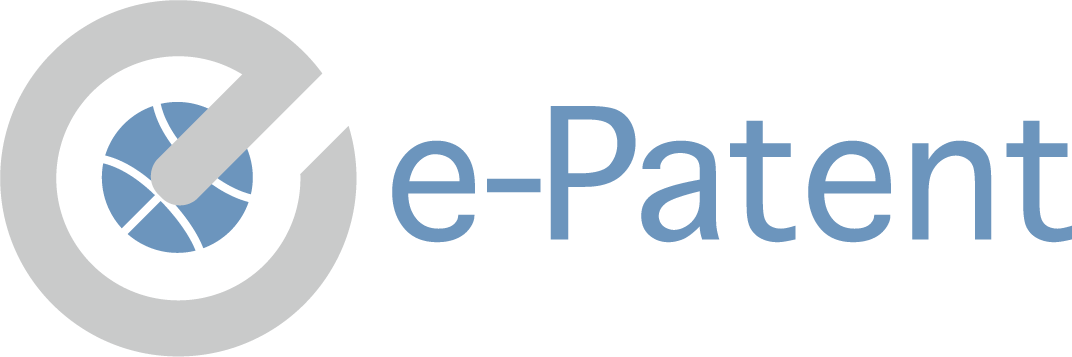当社代表・野崎が日本製薬工業協会主催「2025 ライフサイエンス知財フォーラム」に登壇しました

当社代表の野崎が2025年2月4日に開催された日本製薬工業協会主催「2025 ライフサイエンス知財フォーラム」において「AI時代において求められる知財人材-知財情報分析・IPランドスケープを中心に-」と題した講演の講師およびパネルディスカッションでパネリストを務めました。
「AI時代において求められる知財人材-知財情報分析・IPランドスケープを中心に-」の講演概要は以下になります。
2022年11月のChat GPT-3.5のリリースを機に、生成AIを抜きにして知財人材をテーマとして語ることはできないような状況となってきています。特許庁が2017年に発出した知財人材スキル標準ver. 2.0には、戦略と実行にレベルを分類して知財人材が求められるスキルが記されていますが、これらのスキルは知財機能として具備すべきスキルであって、一人の知財担当者がこの全てをカバーすることが求められているわけではありません。たとえば知財業務(調査・分析中心)に求められるスキルセットとして、「ビジネス力」「情報収集力、検索・分析力」「情報活用力」が挙げられますが、これら3つのスキルすべてにおいて高いレベルを持つ必要はなく、どれか一つに強みを持ち、その他のスキルに対しては興味を持ち、情報を常に入手するような行動が必要と考えます。特にここ10年においては、知財人材スキル標準にも記載されているIPランドスケープが注目されており、従来の知財スキルに強みを持つ知財部門、知財人材は、知的財産への投資や戦略的活用スキルである「ビジネス力」の強化が求められていると思います。
このような環境における生成AIの知財業務への対応可能性・適用可能性を考慮すると、生成AIの知財業務へ与えるインパクトは、もはやこれを抜きに知財業務を語れないステージにあると言えます。たとえば株式会社イーパテントでは知財情報業務において、ChatGPTを始めとした6種の生成AIをその目的と特徴(ハルシネーションの起こし易さ等)に応じて使い分けて活用しています。また特許調査・分析を専門にされていないスタートアップや大企業の方々向けに、ChatGPTを用いて「特許検索式作成GPT」「特許分析軸作成GPT」「特許調査、分析に関するチャットボット」等を作成し、無料開放していますので、気軽に使用していただきたいと思います。
このようにAIを活用して業務が効率化されていく中で、どのような人材やスキルが必要とされるのかについて考えてみました。AIはすべての知財業務を代替することはなく、明細書作成や契約書チェック、特許検索・分析を効率化するためのサポートツールであり、1つの専門性を有するT字型人材が差別化要素を加えて、さらに発展したπ字型・超T字型へシフトするための専門性を引き延ばすツールとなり得ます。このとき差別化に必要なスキルとして、学ぶことによって獲得できるブライトサイドスキル(弁理士・MBA等)とAIが置き換わることができない人ならではのスキル(人や組織に影響を与え、動かす力等)であるダークサイドスキルを磨くことが、これからは重要となってくると思います。
最後に知財分野において生成AIを使いながら、どのように人材育成を進めるべきかについてお話ししたいと思います。企業の知財部門・知財リエゾンや特許事務所などの知財サービス会社の人材育成の対象を、新人・中堅・ベテランに分類することができ、生成AI活用時代においてはこの対象者ごとに必要となる取り組み・育成方法が異なると思われます。特に新人育成においては、始めから生成AIを活用することを学ばせると、AIからのアウトプットの正誤が判断できなくなってしまうため、明細書作成やオフィスアクション対応などの実経験を積ませることが重要となってきます。そして新人の育成を担当する上位者は、いつ頃から新人にAIを使用させるべきかを適切に判断することが求められます。